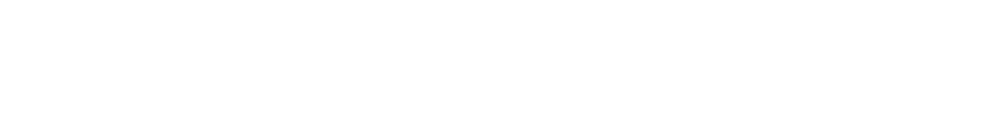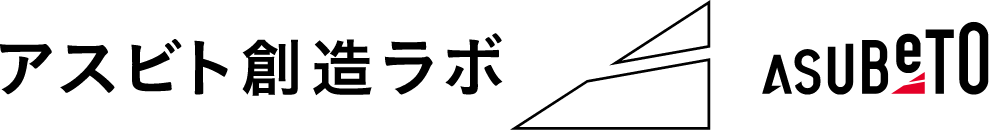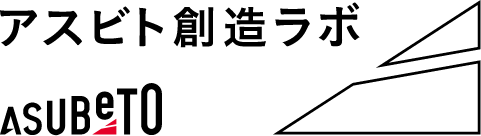劇場と非劇場のシナジーをめざす、映画の新ビジネスモデル
山国秀幸/映画プロデューサー

ASBeTO:22 ものづくり×明日人
誰もが上映会の主催者になれる
映画といえば、劇場やDVD、放映権、配信などで収益を上げるものだと思いがちですが、非劇場(自主上映会)でも多くの観客を集めるシネマソーシャル事業を展開しているのが、ワンダーラボラトリーの山国秀幸さんです。介護や認知症という社会的なテーマで映画をつくり、着実に観客の裾野を広げています。映画業界関係者も驚かせるほどのビジネスモデルをどのように切り拓いてきたのでしょう。
映画を“ビジネス”にしたい
――リクルートから映画業界に入られた経緯を教えていただけますか?
リクルートでは広告営業をしていました。ただ、10代の頃は、オタクといわれるぐらい映画好きだったこともあって、気づくと映画業界に近づいていましたね。まず営業先のゲーム会社に採用担当者として誘われて入社したのですが、異動後はアミューズメント施設の開発を任されて、映画とのコラボなどを経験しました。しばらくして仕事で知り合った映画会社の社長に「うちに来ないか」と。その会社は映画の製作委員会の幹事を担当する会社。映画をつくった経験もない自分に務まるのかと社長に聞いたところ、これからはビジネスがわかるプロデューサーが必要だと言われて転職を決めました。
入社してまず驚いたのは、作品ごとにいくら投資して、どれぐらい回収できたかという収支がまったく検証されていないことでした。経理書類を計算したら、ほとんど赤字。報告すると社長も経理担当者もびっくりしている。作品をつくり続けることでお金を回している――こんなのビジネスじゃない、旧来のビジネスモデルは崩壊していると思ったのです。映画館に依存しない、ネット向けの企画を出したりしたものの、早すぎたのか社長の理解も得られませんでした。そこで2007年、「ワンダーラボラトリー」を設立し、独立しました。「映画をビジネスにする」という目標を掲げて。

「ニュー・シネマ・パラダイス」みたいな世界だ!
――すぐに成果は出ましたか?
最初の10年間はずっとさまよっていました。低予算でアニメを製作したり、いろんなことに手を出していましたが、何をやれば自分の理想が叶えられるかは見えなかった。
とはいえ会社を維持しなければならない。そこで命綱になったのは、ゲーム会社時代に関わった仕事です。パチンコ・パチスロ関係のテレビ番組をネット向けに販売する権利を譲り受けたのです。それでなんとか会社をやりくりしていけるようになりました。
経営基盤が少し安定していく中で、いくつかの映画作品に出資していたのですが、そこでヒントを見つけたのです。2012年に公開された「人生、いろどり」という作品です。舞台は徳島県の上勝町で、農協職員とおばあちゃんが、地元の葉っぱを料理店に販売することに成功するストーリーで、映画館での集客は厳しかったのですが、面白かったのは3カ月に1回上がってくる売上レポート。「非劇場」という項目の売上がぐんぐん伸びていたのです。非劇場って何かと調べたら、市民や自治体などが運営する自主上映会のことでした。
翌2013年に公開された「ガレキとラジオ」も映画館より上映会で広がりました。東日本大震災発生の約2カ月後に宮城県南三陸町で生まれた災害ラジオ局“FMみなさん”をめぐるドキュメンタリー映画です。自主上映会場にいくつか呼ばれて講演したり、対談したりしたのですが、主催者の皆さんは東北を応援しようとか、防災意識を高めようという気持ちで開いてくださっているのですね。来られている方の大半は近所のお年寄りの方々で、映画を見て泣いて、久しぶりだからお茶飲もうと言って帰って行かれる。「ニュー・シネマ・パラダイス」みたいな世界だなって。上映会ってすごく意味があるし、これこそが本来の映画の姿なんじゃないかと思った。それから上映会で成功する映画の研究を始めました。

提供:ワンダーラボラトリー
自主上映会は地域の一大イベント
――自主上映会を成功させる法則のようなものは見えてきましたか?
二つあって、一つは「これは自分たちの映画だ」と思ってくれる「上映会の主催者」がいること。もう一つは、「その映画を見たいと思う人」がいることです。その二つが重なったテーマでなければいけない。「ガレキとラジオ」の上映会は1年ぐらいしか続かなかった。その理由は、「東北を応援したい」という主催者はいますが、残念ながら「震災の映画を観たい」という人が減ってしまったからでした。僕たちがどれだけ「この映画を通じて東北を応援したい」という気持ちがあっても、現実は厳しいものでした。
そんな分析から「介護」や「認知症」をテーマに設定しようと考えました。介護関係に携わる人はたくさんいて、現場のことを知ってほしいというニーズがある。一方、高齢化で認知症に興味がある人も多い。最初はそんなマーケティング的な発想でテーマを決めました。
これまでの映画では介護職といえば、キツく、ツラい仕事としてしか描かれていなかったので、脚色しないと暗い映画になるのかなと思っていました。ところが実際に取材を進めると、それが思い込みだと気づかされました。介護現場にはいろんな感動があるし、キラキラした表情で働く介護職の人たちがたくさんいる。認知症になったら終わりだ、みたいに思っていたのに、症状と付き合いながら日常を生きている人がいる。そんな姿に触れて、大きく人生観が変わり、このテーマにしっかり向き合わなければ失礼だ、これは自分自身のテーマだと考えるようになりました。映画のディテールについても複数の専門家のチェックを受けながら丁寧に仕上げました。
そうして完成したのが「ケアニン」(2017年)です。主人公は新人の介護福祉士。介護、看護などケアする仕事に誇りと愛情、情熱を持って働く人を“ケアニン”という造語で表したのですが、彼が認知症の女性と関わる中で成長していく物語です。映画づくりに関わった人たちが口コミで広めてくれたり、ご覧になった介護職の9割が「同業者に勧めたい」とアンケートに書いてくださったりした。プロから高い評価をいただいたこともあって、上映会は1600カ所を超えました。コロナの蔓延がなければ3000カ所に届いたと思います。
――上映会のことをどんなふうにPRするのですか?
僕は上映会に来た人は潜在的な主催者だと考えているので、「あなたも上映会の主催者ができます」というパンフレットを配ることにしています。SNSを使って主催者を募るという方法は、上映会には向いていないのかなと思います。主催するには会場の手配や集客など、けっこうパワーが必要です。パンフレットを見ながら人と話して力を合わせていく中でようやく実現する。DVD販売やレンタル、配信もしないのは、上映会を増やしたいからです。
上映会の醍醐味は、地域デザインにつながることです。ポスターをつくり、協賛金を集め、中には近所の商店の広告を集めて独自のパンフレットをつくって、そこに主催者の思いを書く……。地域の一大イベントになるのが面白いところですね。
そうした地道な活動が僕たちの映画のブランドとなって、続編である、在宅医療・介護を描いた「ピア」(2019年)、「ケアニン2」(2020年)をつくりました。ただ、コロナ禍で映画館はもちろん、介護現場は上映会どころではなくなったのは残念でした。

映画「ケアニン」「ピア」 提供:ワンダーラボラトリー
省庁・自治体・企業の協力が成功のカギ
――そんな中でよく「オレンジ・ランプ」(2023年)の製作に踏み切れましたね?
若年性アルツハイマー型認知症のご本人である丹野智文さんとの出会いが大きいですね。コロナ禍になり上映会が激減しました。会社の経営が厳しくなったので新作の製作を躊躇していましたが、丹野さんはコロナ禍でも同じ認知症の方々を勇気づけていました。その彼に「全国の認知症の本人たちを映画で勇気づけてほしい」と言われて発奮しました。これまでは介護者目線の作品が多かったので、当事者目線の作品も必要だとも思いました。
いざ企画を進めてみたら、配給会社のギャガさんが、僕たちの自主上映会の実績をみて、こんなやり方があるのかと驚いて、一緒にやろうと言ってくださったのです。これは資金集め、俳優のキャスティング、宣伝、劇場公開などいろいろな面でいい影響がありました。
仕掛けもかなり行いました。まず厚生労働省とタイアップして、映画のポスターを全国の自治体に貼ってもらえるようにしました。自治体の皆さんが認知症への理解を深めたいと考えているのを知っていたからです。太陽生命保険さんが冠協賛してくださったのも助かりました。CMで「この映画を応援しています」と呼びかけてくださった。こうした協力の甲斐あって、多くの方が映画館で観てくださいました。自主上映会に関しても問い合わせが増え、多い日で1日10件以上の問い合わせをいただいています。過去作品と比べても一番反響が大きいですね。劇場と上映会のシナジー効果が得られたと考えています。

©2022「オレンジ・ランプ」製作委員会 提供:ワンダーラボラトリー
世の中捨てたもんじゃない、というメッセージを発信し続けたい
――いまは映画ビジネス単独で黒字化できているのでしょうか?
コロナ禍の影響もあって、大きく利益は出ていませんが、継続して映画をつくり続けることは出来るようになりました。ビジネスモデルとして確立しつつあり、映画の規模も以前より大きくなりました。
ただ、やはりまだ経営のベースは、もう1つの事業の柱である動画配信サイトの企画・運営事業です。シネマソーシャル事業という、このビジネスモデルで映画製作に取り組んでいる人は他にみたことがないので、自分で切り拓くしかないですね。実績を重ねて、このモデルを更に大きくしたいと考えています。
――製作中の新作映画のこと、そして今後の方向性をお聞かせください。
詳しくはまだお話しできないのですが、社会的マイノリティをテーマにした作品です。上映会で多くの方にみていただくスタイルは今まで通りなのですが、作品として映画業界で評価を得られるような方向性をめざしています。劇場でも勝負できて、映画賞も狙えるぐらいの。そうしたチャレンジによって、僕たちが今後映画づくりをする上で選択肢が増え、環境が変わればと考えています。次回作は新たなテーマになるので、これまでの上映会主催者に反応していただけない可能性も考えられます。そのため、映画の舞台となる自治体やテーマに関連する団体と企画段階から連携するなど、様々な手を打っています。
今後はこれまでになかった表現方法にも挑戦していきますが、僕たちが大切にしてきた人間愛、世の中捨てたものではないというメッセージは変わらず発信していきたいです。
(2023年10月3日)

映画「ケアニン」と講演がセットの上映会にて 提供:ワンダーラボラトリー
明日人の目
映画には社会を変える力がある!
「映画には、人生を変える力がある」
映画館のないカンボジアの農村に、映画を届ける活動をするNPO法人World Theater Project代表 教来石小織さんのことばです。
カンボジアの農村の子どもたちに、「将来なにになりたいの?」と聞いたところ、多くの子どもが「学校の先生」と答えたことに驚いたのが、活動を始めるきっかけだったとか。なにしろ子どもたちの周りにいる大人といえば、農業をする家族と学校の先生しかいないのですから、描く夢の選択肢も限られてしまいます。
「知らない夢は、見られない」
そう考えた彼女は、世の中にはたくさんの職業があること、子どもたちにはたくさんの可能性があることを伝えるために、音楽家やサッカー選手が主人公のアニメ映画を届けるプロジェクトを始めたのです。
人生100年時代には、介護や認知症とどう向き合うかが大きな社会テーマになります。私たちはその課題に対して、知らないからこそ、「たいへん」とか「困る」と思いこんでしまう認知バイアスに囚われることもあるのではないでしょうか。現場をよく知る介護者や当事者だからこそわかる大きな「喜び」や心温まる「幸せ」も、そこにはあるはずなのに。
介護や認知の世界を新たな視点で描く山国さんの映画をきっかけに、人生の価値を見つめ直し、「世の中捨てたものではない」とほほ笑む人は、きっと増えるに違いありません。
だって、「映画には、社会を変える力がある」のですから。
アスビト創造ラボ 編集長

PROFILE
山国秀幸(やまくに・ひでゆき)
1967年大阪府生まれ。映画プロデューサー、脚本家。大学を卒業後、リクルートに入社し、広告営業を担当。その後、ゲーム会社や映画会社を経て、2007年、株式会社ワンダーラボラトリーを設立し、代表取締役に。社会課題をテーマにした映画を企画・プロデュースする。「ガレキとラジオ」のあと、2017年に介護がテーマの映画「ケアニン~あなたでよかった~」を製作。2020年には続編「ケアニン~こころに咲く花~」(通称「ケアニン2」)、ドキュメンタリー「僕とケアニンとおばあちゃんたちと。」(2019年)などシリーズ化。2019年には「ピア~まちをつなぐもの~」、2023年6月には「オレンジ・ランプ」などを公開。映画公開に先駆け、原作小説「オレンジ・ランプ」(幻冬舎)を上梓。
- 株式会社ワンダーラボラトリー https://www.w-lab.jp/
- 取材・文/西所正道
- 撮影/阿部稔哉